Vol.31 WHO’S NEXT THE WHO 1971
初の1位を獲得、代表曲が並ぶ、
創造性と進化のピークを示した必聴作。

フーズ・ネクスト/ザ・フー
楽曲、パフォーマンスと、ザ・フーがもっとも創造性を発揮したアルバムであり、彼らの最高作といっていい。もちろん、ブリティッシュ・ロックの名盤だ。全英1位、全米4位。
今では、ファンも評論家も認める名盤であるが、メンバーのピート・タウンゼントは、当初このアルバムのことを嫌っていた。
「これは妥協したアルバムだ。当時、僕らが持っていた最高のものでできているけど、すべてが劇場用のプロジェクト、映画用のアイデアだ」と(でも、最高のものとは認めているね)。
そう言うのも分かる。なぜなら曰く付きのアルバムだからだ。ここに収められた楽曲は、もともとピートが考えたプロジェクト<ライフハウス>のために作られたものであった。
<ライフハウス>とは、風変わりなストーリーを持った、映画、演劇、オペラのようなものだったらしい。しかし、プロジェクトは結局頓挫してしまった。そこで共同プロデューサー兼エンジニアのグリン・ジョンズ(レッド・ゼッペリン、ローリング・ストーンズ、スモール・フェイセスなどの作品を手がけた)が、コンセプトなど持たせずに曲の寄せ集めでアルバムを作ろうと進言して完成させた。
コンセプトのしばりがなくなったおかげで、楽曲のクオリティ優先で選ばれたのだろう。『フーズ・ネクスト』は、「Baba O’riely」、「Won’t get fooled again」「Behind blue eyes」といった、ザ・フーの代表曲(ロック・クラシックスでもある)を含む、充実した内容となった。全楽曲よく作り込まれている印象が強く、埋め草的な曲がない。
ほぼ全曲を書いたピートのソングライティングは冴えわたっており、シンセサイザーやシーケンサーの使いかたのセンスも、この時代にしては進んでいる。
演奏もすばらしく、とくにロジャー・ダルトリーの歌声は表現豊かで、繊細な表情を見せてくれる。こんなに上手い人だったっけと驚いたくらいだ。
ザ・フーは、ハードロックで分類されることが多いが、レッド・ゼッペリンやディープ・パープルと比べると、ずいぶんとソフトでライトである。そのへんが個人的に気に入っているが、反対に本国ほど、日本で人気がないのはそこが原因かもしれない。
このアルバムでも、ちょっとハードなロックンロールナンバーはあるが、全体的には、軽快でメロディやアレンジが際立っている印象が強い。
個人的には「Song is over」、「Getting in tune」(両方とも、ゲストのニッキー・ホプキンスのピアノがいい)といった、のどかな趣きの、少し複雑な展開を見せる曲は気に入っている。
ところで、アルバムのジャケットの写真だが、なぜモニュメントのような巨石に立ちションなのか。何か意味が込められているのかと思ったが、特にないようで、メンバーも何も説明していない。当初は太った裸の女性を使った案を考えていたらしい。こういう不遜なところは、やはりザ・フーらしい。
♪好きな曲
Baba O’riley
ミニマルなシンセのフレーズとヴァイオリンが印象的な高揚感あふれる曲。米国TVドラマ「CSI:ニューヨーク」のオープニング曲。
Won’t get fooled again
邦題は「無法の世界」。シングルカットされ全英9位、全米15位。アルバムは8分半のロングバージョン。米国TVドラマ「CSI:マイアミ」のオープニング曲。
The song is over
ライブでは演奏されなかった(らしい)曲。後半にかけての盛り上がりが素晴らしい。
Vol.30 OFF THE WALL Michael Jackson 1979
名曲、佳曲そろった、元気はつらつ、
楽しさいっぱいのソウル。

オフ・ザ・ウォール/マイケル・ジャクソン
全米シングルチャートトップ10に4曲を送り込んだ傑作、マイケルの実質ファーストソロであり、その後の成功のきっかけとなった作品である。全米3位。
ふり返れば、マイケルにとって最後のソウルアルバムとなった。次作のモンスターアルバム『スリラー』以降は、ソウルの枠を超えて、ロック、ポップスとの融合が図られていく、つまりキング・オブ・ポップへの道へと歩んでいくわけで、その分、ソウルの黒さやしなやかさは中和されていく。
しかし、『オフ・ザ・ウォール』はソウル成分の濃いアルバムだ。ディスコもあり、メロウもありと、この時代らしいブラックミュージックとなっている。きらびやかで楽しさがつまったソウルを味わうことができる。
『オフ・ザ・ウォール』は、ソロアルバムとしては5作目だが、実質的にはファーストソロのようなポジションで扱われることが多い。なぜなら、前作までは主導権はレーベルのモータウンにあったこともあり、マイケルがやりたいことをやれたわけではなかった。
しかしこのアルバムからは部分的にプロデュースも行っており、はじめてやりたいことができた。それが関係していたからなのか、はつらつとした雰囲気に仕上がっている。ジャケットのマイケルもにっこり、笑顔のマイケルなんて、これ以降のアルバムでは見かけない。
プロデュースはクインシー・ジョーンズ。70年代のクインシーはソウルとジャズを一緒にしたような、フュージョン、イージーリスニング中心の傑作アルバムをA&Mから出していた。そのあたりの洗練されたアレンジがここでも発揮されている。
楽曲はダンサンブルでポップな曲、メロウなAOR調の曲など聴いていると楽しくなるものばかり。4曲の全米トップ10シングル(そのうち全米1位が2曲)を出したのも納得できる。
注目曲は、マイケルが作詞作曲をてがけた「Don’t stop till you get enough」。軽快なディスコナンバーでマイケルのファルセットは冴え、独特の節回しでノリノリに歌う。同じくシングルヒットした「Rock with you」、「Off the wall」もメロディとグルーブが気持ちよく、いまではソウルの名曲だ。
シングル曲以外も粒ぞろい。スティービー・ワンダー提供の「I can help it」、デヴィッド・フォスター&キャロル・べイヤー・セイガーといったヒットメイカー作の「It’s the falling in love」も、ポール・マッカートニーがマイケルのために書いた「Girlfriend」(ポールのバージョンは『London Town』に収録)もキュートだ。いずれもシングルカットされたらヒットしていたかもしれない出来ばえだ。
個人的にはマイケルへの関心は『スリラー』あたりまで。ジャクソン5時代を除けば、マイケルは『Off The Wall』1枚で十分だ。マイケルにしても『スリラー』以降、世界的スターにはなったが、トラブル続きで徐々にキワモノ扱いされていく。
それだけに『Off The Wall』でのイノセンスな輝きがいっそう際立つ。マイケルに興味が無くても、70年代ソウルの名盤として聴いてもらえるとうれしい。
♪好きな曲
Don’t stop till you get enough
全米1位、グラミー賞最優秀R&B男性ヴォーカル賞受賞。アレンジもさえている。
Rock with you
全米1位、一晩中、君とロックしたいという他愛もない歌だが、メロディがとてもいい。
It’s the falling in love
パティ・オースティンとデュエット。こういうメロウなポップスも似合う。
Vol.29 Roger Nichols & The Small Circle Of Friends 1968
甘酸っぱいメロディに美しいコーラス、
渋谷系に愛された、浮世離れしたポップソング。

ロジャー・二コルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
キュートで洒落たポップソングがつまった、ちょっとカルトな名盤だ。渋谷系アーティストに愛されたこともあって、日本では何度も再発されるロングセラーのアルバムでもある。
明るいけれど、ほんの少しさびしさが混じったメロディに、美しいコーラス、夢見心地になるような雰囲気…そんな音楽を知らない?と、たずねられたら、このアルバムは必ずすすめるだろう。
今では名盤とされてはいるが、本国でリリースされた当時は売れなかった。ところが、日本では初CD化(1987年)されて以来、幻の名盤のような扱いで知られるようになった。
渋谷系アーティスト、中でもピチカート・ファイブやフリッパーズ・ギターによる愛情たっぷりにリスペクトされたことが大きかった。その影響もあり知名度が広まったのである。その当時HMVやWAVEといったCDショップではけっこうレコメンドされていた印象がある。
グループの中心人物であるロジャー・二コルズは、A&Mレーベルのソングライター、シンガーだった。A&Mは、ハーブ・アルバート、セルジオ・メンデス&ブラジル’66、バート・バカラック、カーペンターズなどが在籍していたことからも分かるように、イージーリスニングや中道的なポップスを得意としたレーベルであった。
二コルズは、66年にマレイとメリンダのマクレフォード兄妹と、スモール・サークル・オブ・フレンズを結成。フォークやコーラスグループから影響を受けた、ドリーミーな三声コーラスと、やさしく美しいメロディ、斬新なアレンジ(マーティン・ペイチやニック・デカロなど)が持ち味だ。
アルバムでは二コルズやマレイのオリジナル曲の他に、ビートルズやラヴィン・スプーンフル、バート・バカラック、キング&ゴフィンの曲も取り上げている。
二コルズの作風といえば、後にカーペンターズに書いた曲のように、しっとりとした少し切なさを含んだメロディが印象的だったが、ここでは「Love so fine」、「Don’t take your time」のような、パッと心が明るくなるようなメロディが際立っている。
とても素敵なポップスがつまったアルバムではあったが、セールスはふるわず、グループは解散した。68年ごろというのは、アメリカ社会は大きな変動の時期であったし、音楽も新しいロックやフォークが台頭してきた時期でもある。そんな中で、浮世離れした中道的なポップスは求められなかったのかもしれない。
ただ、二コルズはこの後、ポール・ウイリアムズとチームを組み、カーペンターズの大ヒットシングル「We’ve only just begun(愛のプレリュード)」、「Rainy days and Mondays(雨の日と月曜日は)」など名曲を生んだ。
そして驚くことに2007年、オリジナルメンバーによって新作『Full Circle』が発表された。みずみずしく美しいメロディとコーラスは健在だった。
それだけでも驚きなのだが、2012年には『My Heart is Home』を発表し、ふたたび驚かされた。今どき、こういうタイプの音楽はあまりないようなので、聴き継がれてほしいと思う。
♪好きな曲
Love so fine
ヴォーカルはメリンダ。なんてキュートなメロディなのだろう!
Don’t take your time
弾むようなメロディに完璧なコーラス。それにストリングスとブラスのアレンジが素晴らしい。
Snow queen
キャロル・キングのソロデビュー前の曲。隠れ名曲でコーラスがとてもエレガント。
このアルバムは、 iTunesにはないので、『Full Circle』と『My Heart is 』から2曲。
ほとんど変わっていない。
カーペンターズに書いた「愛のプレリュード`』をセルフカバー。
これもポール・ウィリアムズと書いた曲
Vol.28 The Joshua Tree U2 1987
アメリカ音楽への憧憬がもたらした、
深みと多様性。名盤にふさわしい風格。

ヨシュア・ツリー/U2
U2がひとつの高みへと到達したことを告げたアルバムだ。アメリカのルーツミュージックへの憧憬から生まれた多様性と深み。はじめから名盤が約束されたような風格が漂っている。全米1位(9週間連続)、全英1位、’88年のグラミー賞アルバム・オブ・ザ・イヤー受賞作。
U2が本領を発揮し、並のロックバンドではないことを示すのは90年代からだ。それでも『ヨシュア・ツリー』は、出世作『WAR』にあったアイリッシュとしてのアイデンティ、むき出しの熱さ、青臭さがほどよく抑えられ、百戦錬磨のバンドのような渋味さえも漂う作風となった。
音楽性に深みが加わり、楽曲は多彩さを増し、スケールも大きくなった。おかげで代表曲にふさわしい曲がずらりと揃った。その理由は2つ。ひとつはR&B、カントリー、ゴスペル、ロックンロールなどアメリカのルーツミュージックからの影響である。
面白いことに、U2のメンバーはそれまで、アイルランドやアメリカのルーツミュージックに興味がなかったという。ところが、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーンなどとの交流から、アメリカ音楽の奥深さにひかれていくようになり、曲づくりに反映させた。
ふたつめはプロデュースだ。前作に引き続きブライアン・イーノとダニエル・ラノワが起用された。前作『焔(ほのお)』で創り上げた、アンビエントやミニマル・ミュージック的なデザインが施された音空間は、今作でみごとに曲と溶け合いサウンドカラーを決定づけている。
斬新な音響によって、U2のまっすぐな熱さ(時として聴き手を疲れさせる)がコーティングされ、静謐と情熱が絶妙に交じり合ったサウンドが生まれた。
聴きどころは前半だ。冒頭からの4曲の流れが素晴らしい。オープニングの高揚感が持続され、早くもクライマックスを迎える。いずれもライブでは、オープニングや終盤を盛り上げる、とっておきの曲だ。以前、東京ドームで観たライブでも、終盤の「Bullet the blue sky」、「Where the streets have no name」には鳥肌が立ったものだ。
後半は前半と比べれば少々地味だが、ギターリフが心地よいグルーブを生む「One tree hill」や、初期のサウンドを思わせる「In god country」など粒ぞろいだ。
ジ・エッジのギターもさらに進化している。細かなカッティングは打楽器のように強烈だし、アルペジオからのフレーズはディレイなどエフェクターの駆使によって、浮遊感のある響きをもたらしている。バリバリとソロを弾くタイプではないが、革新性をもたらした名ギタリストだと思う。
アメリカ音楽への旅は次作『魂の叫び』で一応終わる。次なる巡礼の地はヨーロッパ。U2は『アクトン・ベイビー』をベルリンで録音、エレクトロニックなダンスビートをまとった新しいサウンドを披露した。アイデンティティをめざして、アメリカ、ヨーロッパへ移っていく様は、デイヴィッド・ボウイの辿った道と同じで面白い。
♪好きな曲
Where the streets have no name
荘厳なイントロから疾走感ある展開が素晴らしい。2002年のスーパーボウルでの演奏は感動的だった。
I still haven’t found what I’m looking for
邦題「終わりなき旅」。分かりすく親しみやすい曲で、シングルカットされ全米1位。
With or without you
穏やかな始まりから、徐々にエモーショナルになって聴き手を鎮めるように終わる。なんてカッコいい展開。シングル第2弾で全米1位。
Vol.27 Born To Run Bruce Springsteen 1975
アメリカの夢と挫折と、ロックンロール、ソウル、
R&Bへの限りない愛が込められた青春ロック。

明日なき暴走/ブルース・スプリングスティーン
ロックへのリスペクトあふれたサウンド、そして閉塞からの脱出と希望を表現したみずみずしい歌に心つかまれる。ボスこと、ブルース・プリングスティーンの出世作にして、アメリカンロックの大傑作。全米3位、全英17位。
『明日なき暴走』は3作目のアルバムだ。デビュー作も2作目も内容は高く評価されたが、セールスはいまひとつ。それでも、ライブの評判やラジオでのプロモーションが功を奏して、状況は良い方へと向かっていた。
しかし、ボスは煮つまっていた。「レコードの発売日はたった1日だけど、レコードの中身は永遠に残るんだ」という完全主義ゆえの姿勢がそうさせた。そこで信頼厚いジョン・ランドゥにプロデュースを乞う。
ランドゥはこのときローリングストーン誌の有名な記者で、彼の記事の中のフレーズ「僕はロックンロールの未来を見た。その名はブルース・スプリングスティーンという」は、ボスを表舞台へと引き上げた。ランドゥはボスにこうアドバイスをした。「自分のやりたいことを迷わず貫きとおせ」。
ボスは後にこのアルバムについて「『明日なき暴走』では、ディランのような詩を書き、フィル・スペクターのようなサウンドを作り、デュアン・エディのようなギターを弾き、そして何よりもロイ・オービスンのように歌おうと努力した」と語った。
20カ月という難産の末、アルバムは完成。その言葉どおり、ロック愛に満ちた、粒ぞろい楽曲が揃った。後に代表曲として、ライブの定番になった曲ばかりだ。
メロディもアレンジもよく練られている。ボスはエルヴィス・プレスリーやチャック・ベリーから、ボブ・ディラン、さらにスタックスやモータウンのソウル、R&Bまで、幅広い音楽から影響を受けており、今作でもそれがみごとに活きている。
Eストリート・バンドの演奏も素晴らしい。特に新加入のマックス・ワインバーグとロイ・ビタンの存在は大きい。ワインバーグのドラムはさらにリズムをダイナミックにしているし、ビタンのピアノやオルガンは、クラレス・クレモンズのサックスとともに、ボスのサウンドの個性となっている。
ボスが一貫して歌ってきたのはアメリカだ。若者、労働者、帰還兵、時には犯罪者などアウトサイダーの視点から、アメリカの夢と挫折にまつわるストーリーを、掌編を思わせる歌詞で表現してきた。
今作では閉塞状況の若者の痛みや絶望が描かれているが、姿勢はあくまでポジティブで希望はあると呼びかけている。
ボスのメッセージは「手遅れかもしれないが、それでも希望に向かって駆け抜けろ」だ。言うなれば、明日への疾走。そのために俺たちは生まれてきたのだと。
だから『明日なき暴走』という邦題は誤解を与える。これではやけくそになった若者が暴れまくるイメージだ。あなた、そんな歌を聴きたいか?
♪好きな曲
Jungleland
ボスの曲の中で1番好き。9分半のドラマティックな展開、間奏部のクレモンズのサックスに感動せずにはいられない。
Born to run
語り継がれるべきロッククラシック。スピード感とフィル・スペクターを思わせる音響にしびれる。この1曲に半年も費やしたとか。全米23位。
Tenth avenue freeze-out
邦題「凍てついた十番街」。自伝的な内容で、サザンソウルを思わせるホーンがいい味を出している。
Vol.26 Lark’s Tongues in Aspic King Crimson 1973
即興性を取り込んだ、新たな方向性は
攻撃的でダイナミック。
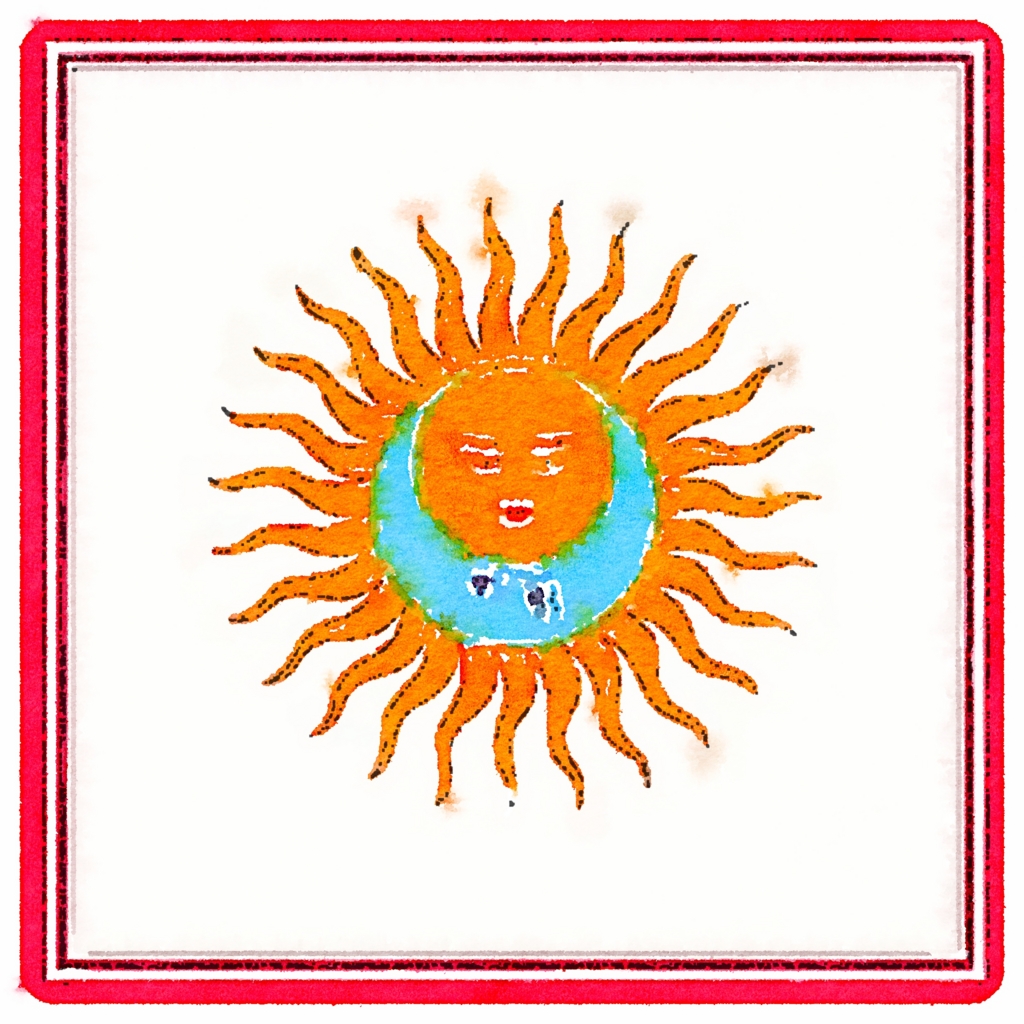
太陽と戦慄/キング・クリムゾン
前衛音楽のようなアプローチを編み込んだ、複雑に構築されたサウンドが展開。重量感とダイナミックさを従えたジャズ・ロックに近いスタイルでクリムゾンは生まれ変わった。
クリムゾンで一番好きなアルバムは、『レッド』ではあるが、アルバムごと一番多く聴くのは『太陽と戦慄』だ。はじめはとっつきにくかったが、ロックらしいアグレッシブさと、先鋭的なジャズ的な要素がいい按配で、意外に聴き疲れないのが理由だ。
長尺のインストナンバーと歌もの、それぞれ3曲ずつの構成だが、それまでクリムゾンの持ち味であった叙情性は後退している。代わりに全編ドライなタッチで攻撃的なサウンドが目立っている。聴きどころはやはり「太陽と戦慄」パート1とパート2だろう。
メンバーは前作時とは、ロバート・フリップ以外すべて交替したが、演奏の質は格段に強化された。
ジョン・ウェットンとビル・ブルフォードが打ち出す強靭なリズムと、フリップのヘビーなカッティングが紡ぎだすエッジの効いた空間に、ジェイミー・ミューアの神出鬼没なパーカッションが舞い、デイビッド・クロスのヴァイオリンが緊迫感を添えるという、実にスリリングなアンサンブルが実現した。
楽曲の大半は、緻密に構築されてはいるが、即興的なアクセントがほどよいさじ加減で加えられている。整理されているぶん、だらけたソロパートがなく、長尺ナンバーでも引き締まっているので聴きづらくはないし、意外に時代がかっていない。
また、全体的にヘビーな印象があるものの、「土曜日の本」、「放浪者」という叙情性をもった歌ものがいい箸休めになっており、重さがもたれないのもいい。
ただし、はじめてのクリムゾンには適しているとは言えない。やはり、歴史的名盤『クリムゾン・キングの宮殿』から聴くのが良い。
新メンバーによる新しい方向性でスタートしたクリムゾンだったが、サウンドの要を担っていたミューアが脱退したので、次作以降は違ったサウンドになったものの、構築と即興のアンサンブルは受け継がれていく。
全米61位、全英20位とチャートでは比較にならないが、このアルバムでようやくフリップは、『クリムゾン・キングの宮殿』(全米28位、全英5位)の重石から解放され、次へと進める確信が持てたのではないか。
ところで邦題『太陽と戦慄』は、原題(ゼリーの中のひばりの舌:古代ローマで人気のあったらしい料理)の意味とは全く違う。日本のレコード会社の担当ディレクターがジャケットのデザインを眺めて、直感で名付けたとのこと。
もっとも、思わせぶりな原題もなんとなく思いついたものらしい。しかし、原題、邦題ともに、コンセプチュアルなアルバムと思わせてしまう説得力があるのも事実で、実に面白い。
♪好きな曲
Lark’s Tongues in Aspic Part2
地鳴りを響かせながら大軍が押し寄せるようなアグレッシブなインスト。ライブの定番で、クリムゾンの代表曲。ポルノ映画「エマニエル夫人」のサントラで盗用され裁判沙汰になった。実際に聴いた時、あまりにそっくりで笑った。
Lark’s Tongues in Aspic Part1
アルバムの雰囲気を最も表したインスト。13分と長尺だが、スリリングな展開が次々と繰り出される。
Easy Money
歌ものだが、中間の長いインスト部分は、ミューアやフリップのさえた即興を聴くことができる。トヨタの国内のCMで使われた。
Vol.25 The Nightfly Donald Fagen 1982
50年代のジャズやR&Bテイストの
サウンドに込められた、サバービアンの夢想。

ナイトフライ/ドナルド・フェイゲン
スティーリー・ダン解散後に出した、フェイゲンのファーストソロは、フランク・シナトラが歌っても似合いそうな、50年代のR&Bやジャズをコンテンポラリーなサウンドで再現したようなポップス色濃いアルバムとなった。全米11位。
『ガウチョ』をリリースした翌年の1981年、スティーリー・ダンは解散。『ガウチョ』は、前作『Aja』で到達した洗練の極みを突きぬけ、極北まで行ってしまったような作品になった。偏執的なレコーディングとやり過ぎともいえる構築美が、心地良さまで奪ってしまった。
その1年後に出たフェイゲンのソロアルバムは、『ガウチョ』とうって変わって、実に聴き心地の良いAORサウンドに仕上がった。
フェイゲンによると「50年代後半から60年代初めにかけて、アメリカ北東部にある街の郊外で育った若者が、抱いていたはずのある種のファンタジー」がアルバムのテーマだ。
その言葉どおり、サウンドは全体的に50年代、60年代のジャズやR&Bテイストが色濃いもので、ドリフターズの「Ruby Baby」を除いて、すべてフェイゲンのオリジナルだ。
スティーリー・ダンのアルバムの方が似合う曲も少しあるが、大半はジャズやR&Bのスタンダードナンバーと言われても違和感のない曲が揃っている。
ここには、スティーリー・ダンのような変態的な緻密さはほとんどなく、スリリングな演奏もない。ラリー・カールトンなど名うてのミュージシャンたちを贅沢に起用してはいるが、歌を前面に出した、しゃれた雰囲気のサウンドになっている。
ただ、シニカルな視線は健在。たんに80年代から見た50年代へのノスタルジーではない。50年代とはアメリカ史において繁栄の時代であり、世界戦略の礎が築かれた時代だ。アメリカの豊かさのイメージの原点でもある。
そうした輝きは一方で影を生み、闇へと肥大して、混乱の60~70年代を招く。そのあたりのことは著名なアメリカのジャーナリスト、ハルバースタムの力作『ザ・フィフティーズ』に描かれており、『ナイトフライ』にも通底している。
歌詞や題名に<山の手の住宅街の殺人事件>、<共産主義者がミサイルを押したときに>、<ニューフロンティア(J・F・ケネディが掲げた政策名)>といった言葉が登場することからも想像できるとおり、豊かさの象徴の一つでもある、サバービアン(郊外生活者)の夢想には、やはり、ほのかな恐怖も見え隠れする。
『ナイトフライ』ですっかりリハビリしたかに思えたフェイゲンだが、その後は引退同然で次作が出たのは1993年。相棒のベッカーも同時期、ドラッグ中毒で療養生活とさんざん。『ガウチョ』の後遺症は予想以上だったのか。
アルバムジャケットに漂う、エドワード・ホッパーの絵のような空虚感は、無理に明るく振る舞おうとしたために、余計に喪失感が深まった姿の表れではないか…というような深読みも楽しめる『ナイトフライ』なのであった。
♪好きな曲
I.G.Y
ポップなメロディとレゲエのリズムにのって、素晴らしい時代がやってくる~と歌われるが、それ自体が皮肉かも。シングル曲で全米26位。
Green flower street
アルバム中最もスティーリー・ダン度の高い、R&Bタイプの曲。ギターソロはラリー・カールトン。
Walk between raindrops
弾むようなメロディとスイングするオルガンジャズのようなグルーブが心地よい。








